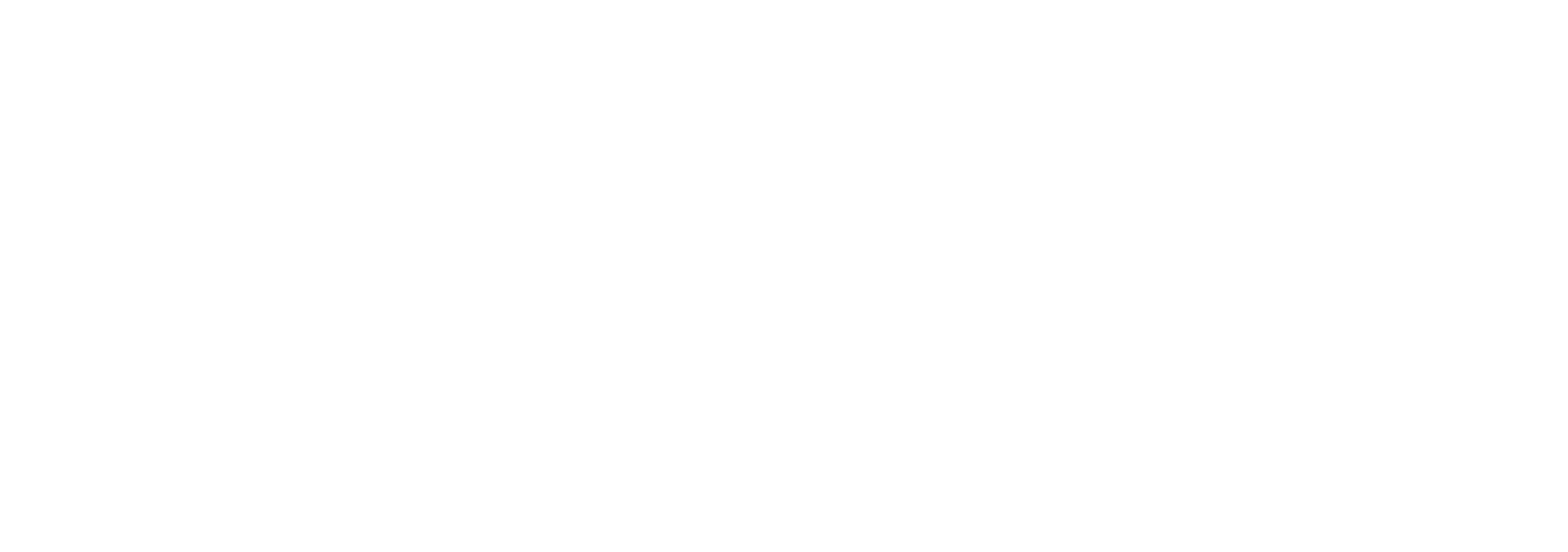若い冒険者たちは未知のフィールドに果敢に挑む!

注目の探究学習
高校レベルを超えてしまった探究学習
探究学習が、従来の教育の枠を大きく超えつつある。社会の深層に切り込む独創的な視点と、リアルな現場への果敢なアプローチで、高校レベルをはるかに超える学びを実現している学校がある。主体的に課題を発見し、深く考察する力を育む探究学習は、未来を切り拓く人材育成の重要な手段となっている。海外フィールドワーク、社会課題の徹底的な調査、斬新な研究テーマの追求など、生徒たちの知的好奇心は驚くべき広がりと深さを見せているのだ。本稿では、独自の探究学習に取り組む6校を紹介。それぞれ「社会の光と影という現実に触れ、深い思考力を育むイギリス縦断フィールドワーク」「日本人の知らないタンザニアの日常に飛び込む中高生たち」「アジア現代史と庶民生活に“何でも見てやろう精神”で迫る若者たち」「ハイレベルな探究学習で奇抜な研究テーマが次々と生まれる秘密」「大学レベルの研究力に自由な発想が加わることで予感される驚きの成果」「“探究から研究へ” をスローガンに大学での研究力も視野に入れた探究学習」をテーマにユニークかつ独自の教育を紹介している。

社会の光と影という現実に触れ、深い思考力を育むイギリス縦断フィールドワーク
巣鴨中学校 国際教育
International Education
2024年度から、「冒険・自立・国造り」をテーマに2週間をかけてスコットランドからロンドンまで南下し、英国の歴史や文化を体感・思考する「巣鴨ビヨンド・ボーダーズ(以下SBB)」をスタートさせた。現地で指導に当たるのは、英国イートン校サマースクールの最高責任者を務めたチャーリー先生をはじめ、現役のイートン校体育科主任で地理も教える教師、イートン校出身でイギリス名門パブリックスクールの一つウェリントン校の現役歴史教師の3名。巣鴨のイートン校サマースクールで構築された人脈から錚々たる面々を揃えた。事前学習も充実し、オンラインでチャーリー先生との1か月半をかけた事前セッションに参加。その上で、宗教、帝国主義、統治などの8つから探究テーマを決めて出発する。
最初に行われるプログラムは球技スポーツ。英国パブリックスクールのラグビー、ボート競技といった授業で重視されるのは、チームワークの構築だ。スポーツを通じたチームワーク構築のプロセスは、実社会で新しいチームとプロジェクトを遂行する際の協働の本質と類似しており、将来の社会で求められる柔軟な人間関係構築力と課題解決能力を育む貴重な経験となっていく。
また訪問先の町では教会などの建築物を見学し、宗教と都市や人々との関係を考察するほか、心の拠り所だった当時の教会の役割についても学ぶ。特にバイキングの来襲時、貴重な書物等をダラム大聖堂に移動させ死守した歴史は、文化や思想、精神性の大切さを物語る。これは社会や国の核となるものが何であるかを潜考する端緒となっていく。
一方、移民が最初に辿り着く町ともされるブリックレーンは、様々な国の飲食店が立ち並ぶだけでなく、落書きも多い。生徒たちは「怖い」と口にしたが、その背景には居場所のない若者たちの不安や不満があるのかもしれない。目の前の事象や行動はその発露に過ぎず、本質を見極めるための議論も促した。さらに炭鉱が閉鎖された町は政府の支援策により一見、整備され美しい。だが実情は治安の悪化や雇用問題を抱えた町だという。かつては繁栄を見せた産業が斜陽となった時、町の整備や支援金が本質的な解決策になり得るのかを考える機会となった。
バイキングの影響が残る町・ヨークへも足を運んだ。異文化の流入は経済の活性化にはつながったが、文化や価値観、生活習慣の違いにより社会的秩序の乱れも生じた。異文化流入は経済面と社会秩序双方の観点から考える必要性があることを学んだ。
こうした体験は、町や国はどのように形成されるのかを考えるヒントとなる。移民が自分の文化を変えずに広めていくのは自然の成り行きであり、当然そこには摩擦も起こる。人口に膾炙する“多様性”への疑問や国際人とは何か、自国文化の理解、本質を見極める思考の大切さを探究する端緒を得ていくのだ。
プログラム期間中、生徒たちは〈観察→まとめ→議論→内省〉という学びのサイクルを毎日行う。同行する教師たちは現地で歴史的あるいは生態系の背景などの説明を必要最低限にとどめる。これにはobservation skills(観察技術)、自分の目で見て気づく力を身につけさせる狙いがあるのだ。その上で、各班に一人付く名門大学生のグループリーダーと班ごとに随時議論し、1日の日程を終えると3人の先生が加わり、生徒へ問いかけ、さらに深い内省へと導いていく。
英国の歴史、文化、社会の深層に触れながら、本質的な学びを実践的に経験し、グローバル社会を生き抜く力を養うSBB。帰国後には探究テーマのビデオプレゼンテーションを作成し、チャーリー先生からのフィードバックを受け取ることで、生徒らの学びはさらに深化し、国際的な視野と思考力を獲得していく。
(文/松岡理恵)

日本人の知らないタンザニアの日常に飛び込む中高生たち
足立学園中学校 国際教育
International Education
『志共育』を教育方針に掲げる足立学園中学校。青年海外協力隊員としてラオスに赴任したキャリアを持つ原匠教諭は、英語圏に目を向けがちな海外研修先を洗い直し、アフリカスタディ―ツアーを立ち上げた。目覚ましい経済発展の陰で、人口、貧困、食糧、環境、教育、紛争など多くの課題を抱える世界の国々の縮図とも言えるアフリカから多くの知見を得てほしい、という思いの結実したプログラムだ。
2024年7月の第3回ツアーは、中3~高2の計11名でタンザニアを訪問した。州都の見学を経て渡ったザンジバル島では、数奇な歴史を持つ美しい街並みと奴隷貿易の遺構が見せる光と影に触れた。巨大なカルデラに多様な野生動物が棲息するンゴロンゴロ保全地域、マサイ族の言葉で「果てしなく広がる平原」を意味するセレンゲティ国立公園の広大な自然に身を置き、日本では決して体験できない大きなスケールを五感で感じ取った。さらに在タンザニア日本国大使館を表敬訪問し、三澤大使からタンザニアの国民性や人々の自信の源も伺った。
そしてハイライトとなったのは、キハラカのセカンダリースクールで体験した"プチ留学"だ。生徒数980名の共学校での2日間の留学では、公用語であるスワヒリ語の授業を受け、学んだ自己紹介や日常会話のための言葉を使い、現地のクラスメイトと1対1で話す。実践に満ちた学習で初めてのスワヒリ語が自然に身に付くのを経験した。午後には校庭でサッカーの国際親善試合。「大勢の現地生徒が観戦してくれていて緊張した」「疲れたけれどとても楽しかった」などの声が聞かれた。翌2日目には快晴の下、木陰に並べた机でお互いの文化を紹介し合い、さらには校庭で国家や校歌の斉唱、持参した野球のグローブとボールを用いてのキャッチボール、けん玉の技の披露などを行った。現地生徒もサッカーのリフティングや民族ダンスでこれに応え、互いに実体験することで双方の文化に触れる機会となった。
そのほか、硬いマホガニーをノミで彫るマコンデ族の彫刻体験、アフリカ絵画の制作体験、家庭料理体験、デイケア施設での園児との触れ合いなど文化交流も多岐にわたる。「世界の見方が変わった」「困難なことに対しても前向きになった」「異なる人種の人を含めどんな人でも受け入れられるようになった」など、生徒たちはより広い視野を獲得した様子だ。保護者からも「親に頼らず自分で考えて、自分の意見を言うことが増えた」と変化に驚く声が寄せられ、「親にとっても学びのあるツアー」との評も聞かれた。
帰国後の探究論文にツアー体験を活かす生徒や、「英語をもっと勉強して将来は外国で働きたい」と志す生徒もいる。第2回のツアーリーダーを務めた生徒は、小学生のときに抱いた国境なき医師団へ参加するという夢を、“志”として自覚する瞬間を体験した。体調を崩した仲間に付き添って訪ねた病院で施設見学を直談判し、そこでタンザニア農村部の医療に私財を投じたアメリカ人医師に出会ったのだ。理想の姿を目の当たりにして“志”が高まるとともに、目指す人物像を見つけたというこの生徒は、探究論文のテーマを『タンザニアの乳児死亡率を下げるのに何ができるのか』に定め、自らの“志”をも探求していくことになったのだ。
「衝撃の連続に自身の殻を揺さぶられ、人と人との真のコミュニケーションを通じて大きな価値観や人間性に気づき、新たな志を胸に帰国。これが毎回のツアーで起こる」と成果を語る原教諭。価値観がアップデートされ、より前向きな姿勢を身につけた生徒たちは、これからの社会にインパクトを与える存在になっていくに違いない。
(文/高島正人)

多摩大目黒中学校の海外プログラムは、2024年新たにベトナムやインド、インドネシアが加わり、計9か国に拡大した。特にベトナム修学旅行とインドスタディツアーは、他校と一線を画す取り組みとして注目に値する。
高校2年のベトナム修学旅行では、戦跡や戦争博物館の見学、ベトナム戦争時に米軍が散布した枯葉剤の影響で結合双生児として生まれたグエン・ドクさんの講話を通じて平和について深く考察する。「現在のアメリカをどう見ているか」など、生徒たちは戦争と平和について質問を投げかけ、対話を通じて平和の尊さを実感していく。また、日本企業の駐在員との懇談では「海外で働くこと」の醍醐味や課題について、具体的な体験談に熱心に耳を傾けた。
貧困の現実に迫るインドスタディツアーには高校1・2年生計17名が参加、生徒たちの世界観を大きく変えることとなった。メインストリートの近代的な町並みのすぐ裏で出会った物乞いの子どもたちの姿に衝撃を受けながらも、生徒たちは単なる同情で終わらせることなく、現地の人々へ果敢にインタビューを重ねていく。その過程で、本当に貧しい人々はペットボトル自体が貴重な生活用品となるため欲しがるのに対し、身なりの整った物乞いの人々はペットボトルに関心を示さない現実が見えてきた。こうした綿密な観察を通じて、生徒たちは貧困の実態により深く迫っていった。
民営のアフタースクールでの体験は、さらに深い気づきをもたらした。将来の夢を尋ねると、答えの多くが「医師」「教員」「警察官」といったわずか数種類の職業しか知らず、そもそも文字の読めない子どもが多いという現実に直面する。知識や情報から切り離されている状況が、将来の選択肢をも限定してしまうという気づきを得た生徒たち。その解決には「教育」が鍵となるという仮説を導き出した。「こうした問題意識は、大学進学後の研究テーマにもなります。実際の体験から導き出された仮説を検証し、解決策を探る。そしてアジアの課題を日本の問題として捉え、より深く研究を進めていく。そんな探究心こそが大切」と田村嘉浩校長は語る。
「世界各国の社会問題だけでなく、優れた面も見て、日本の課題解決に生かしてほしい」という元・経済産業省のキャリア官僚だった田村校長の言葉には、次世代リーダー育成への深い思いが込められている。多摩大学目黒中学校の国際教育は、単なる体験ではなく、社会課題の本質に迫る「探究」としての海外研修の在り方を示す、私学教育のロールモデルといえるだろう。
(文/佐久間香苗)

興味関心に従ってテーマを決め1年かけて探究していく「パーソナルプロジェクト」は、長年重視してきた探究活動にIBの要素を盛り込んだ山梨学院独自のカリキュラム。活動の主体は生徒にあるが、教員の関わり方にも特徴がある。例えば探究活動で最も重要とされるテーマ設定。入学直後、「何をしたらいいかわからない」と訴える1年生とは根気よく会話を続けながら興味関心を掘り起こし、『こんなことに興味があったんだ!』という生徒自身の気づきにつなげていく。常に肯定しながら導くことで、生徒は自由な発想を臆することなく口にすることができ、それが、ときに思いもよらないテーマに発展することもあるという。
活動が始まると、自然、科学、工学、人文、歴史など、幅広い分野に及ぶ多様なテーマを、全教員がチームとなってフォロー。多角的な視点から助言を与えつつ自信を持って活動に取り組めるよう背中を押す。こうした指導により、生徒は自発的に探究活動に勤しむようになり、関連施設に足を運ぶ、アンケートを通じて統計的な調査を行う、実験や栽培・飼育を行う、製作するなど、実に様々な手法を用いて、各々の探究のゴールを目指すようになるのだ。
成果を論文にまとめる際、大学でも通用する研究手法や論文作成のマナーを習得させることも注目ポイントだ。活動の締めくくりは、新たに資料を作成してのプレゼンテーション。クラス発表、学年発表を経て年度末に行われる全校発表は、優れた研究が新たな発想を生み「来年は自分も…」という意欲につながる、成長の機会ともなっている。
「この取り組みの最大の目的は物事を深く知りたいという探究心を育むことですが、それ以外にも、自己肯定感の向上や発想力の進化、視野の広がり、仲間との絆など、実に多くの財産を生徒たちにもたらしてくれます。1年次に経験した自身の興味への探究が、2年、3年と経過するなかで研究へと進化し、好奇心から始まった活動が、キャリアへとつながる例も珍しくありません」と吉田正校長は語る。
奇抜な発想に驚かされることも多いという。昨年度も耐震・免震・制震の構造を分析して、揺れない建築物の製作に取り組んだ生徒や、ウールをリサイクルするために、羊毛を使って花を咲かせることに挑戦した生徒がいた。過去には、1年次にロケットの打ち上げに挑戦した生徒が、2年次に高度を求めて二段ロケットを製作し、3年次には付加価値をつけ、カメラを搭載したロケットで空中撮影をするまでに研究を深化させた例や、ぶどう栽培を通してジベレリン処理の方法や時期によって収穫時期をずらす研究をした生徒が、東大農学部に進んで関連する研究を続けている例もあるという。
こうした活動に対し、同校では、PTAの寄付による教育振興基金を設立し、自らの発想を「やってみたい」と訴える生徒への資金的な支援も始めており、さらなる発展が期待される。
(文/荻原美穂)

三田国際科学学園の教育の特徴は、根幹となるコンセプト「THINK&ACT」に集約されている。知識を活用して論理的に考え(THINK)、問題解決やさらなる課題の発見につながるよう実践する(ACT)。これらの力を育む環境が、国際感覚を養う「INTERNATIONAL」と論理的思考力を養う「SCIENCE」で支えられるように、しっかりと構築されているのだ。
「INTERNATIONAL」とは、生徒の3割以上を占める帰国生と38名(2025年度)のインターナショナル教員を擁する国際性の豊かさを活かし、一般生と帰国生が日常的なコミュニケーションを通じて相互に高め合うことのできる、秀でた学校環境だ。「SCIENCE」とは、あらゆる問題の解決と興味の探究に欠かせない科学的アプローチサイクルを身につけること。全生徒が中1から取り組む「サイエンスリテラシー」の授業において、探究の作法を訓練する。
中学入学後の生徒は、インターナショナルサイエンスクラス(ISC)とインターナショナルクラス(IC)の2つのクラス編成の中で学び、2年次になるとISCのなかでも理数系や情報分野に強い関心を持つ生徒は、メディカルサイエンステクノロジークラス(MSTC)に在籍できる。ここでは、サイエンス研究に特化したゼミナール「基礎研究α」で自ら調査と研究を行って紀要にまとめるという一連の探究体験を積み重ねる。研究テーマを高1・2の「基礎研究β」へ引き継いで、4年がかりで取り組むことも可能であり、新時代を担う若者の研究力と探究力の醸成を後押ししている。
実際に、ISEF2024(国際学生科学技術フェア)に日本代表の一人として参加した生徒も輩出している。「深掘りして底を突き抜けるまで興味を追い続け、研究の所作を身につけてほしい」と語る辻敏之教頭の期待を実践し、『疾患原因となるアミノ酸変異の解析』の研究が評価されたKさんだ。在学中から東京大学で研究をしていたKさんは2025年、東京大学理科Ⅱ類に進んだ。
そして「SCIENCE」的着想をより得やすい環境作りに尽力する同校が今進めているのが、大橋清貫学園長の「発想の自由人たれ」という言葉を具現化する3階建ての「ゼロワン」の増築だ。1階はものづくり空間として、発想を形にする3Dプリンターなどの道具が揃う。2階はブレインストーミングやディスカッションを活発に行える空間となっている。3階では静かな空間を提供できるように工夫されている。様々な思考形態に応じて自由な発想を促す仕掛けを随所に施し、生徒たちが発想以外の余計なことに煩わされず、とことん集中できる工夫を凝らしたという。
「サイエンス思考とコミュニケーションの場を統合するこの環境から、新しい発想の成果物が出てきてほしい」というMST部長・サイエンス教育責任者でもある辻敏之教頭の願いは、次代の生徒たちによって必ずや実現することだろう。
(文/高島正人)

「探究から研究へ、そして未来を創る人となる」をスローガンに掲げ、探究学習を充実させてきた順天中学校は、スーパー・グローバル・ハイスクールの指定校実績を持ち、文理を問わずにグローバルを視野に入れた探究活動を推進してきた。高校では理数探究、英語探究、総合探究の3つの学びの機会を整え、生徒たちは自分の関心や興味を自由に追い求めて様々な実績を上げている。
中でも理数探究の研究は注目に値する。Nさんは高1から淡水系における自然環境への影響について、ミドリムシを用いた環境アセスメントの探究活動に取り組んできた。Nさんは日焼け止めに使われているベンゾフェノンという化学成分が河川に及ぼす影響に着目し、ミドリムシで測定する調査を行った。その研究成果を「つくばScience Edge2024」で発表したところ、環境部門で第1位を獲得。さらにオーストラリア・ブリスベンでの国際発表会にも招聘され、見事受賞した。
雷をテーマにしていたAさんの場合は活動を学外にも広げ、他校生との共同プロジェクトに参加した。宇宙線イメージング検出器を開発し、これがスイス・ジュネーヴにあるヨーロッパ原子核共同研究所(CERN)が募集するコンテストを通過したのだ。そして日本人として初めて素粒子実験提案が採択され、CERNでの実験に招待されるという快挙を成し遂げた。現地では2週間ほど滞在し、素粒子物理学者のサポートのもと、実際にCERNの大型加速器施設で実験を行う経験をした。
同校の探究学習について教育支援センター長の片倉敦教諭は、「探究を単なる調べ学習の延長で終わらせたくない。研究の道筋をつけて高校を卒業し、大学での学びにつなげてほしい。たとえ高校と大学で扱うテーマが変わろうとも、探究で習得したアカデミックスキルや思考力は必ず生きる。テーマや仮説の立案に始まり、研究や調査実験、結果を導くところまで、独自の切り口や問いを見つけながら進められるようになってもらいたいと思っています」と、大学でのハイレベルな研究も視野に入れた研究力の育成への思いを語る。
(文/編集部)