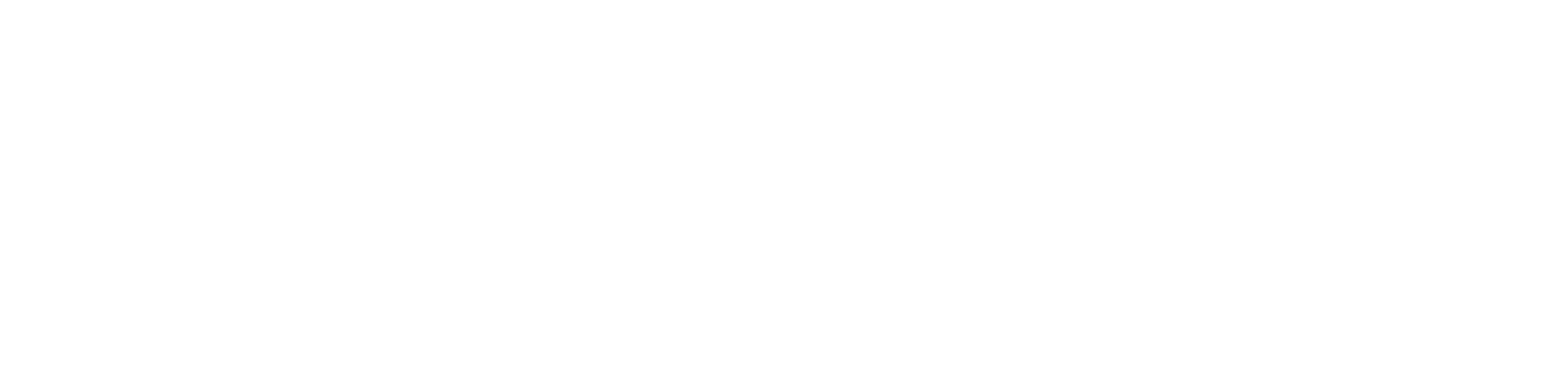海城中学校
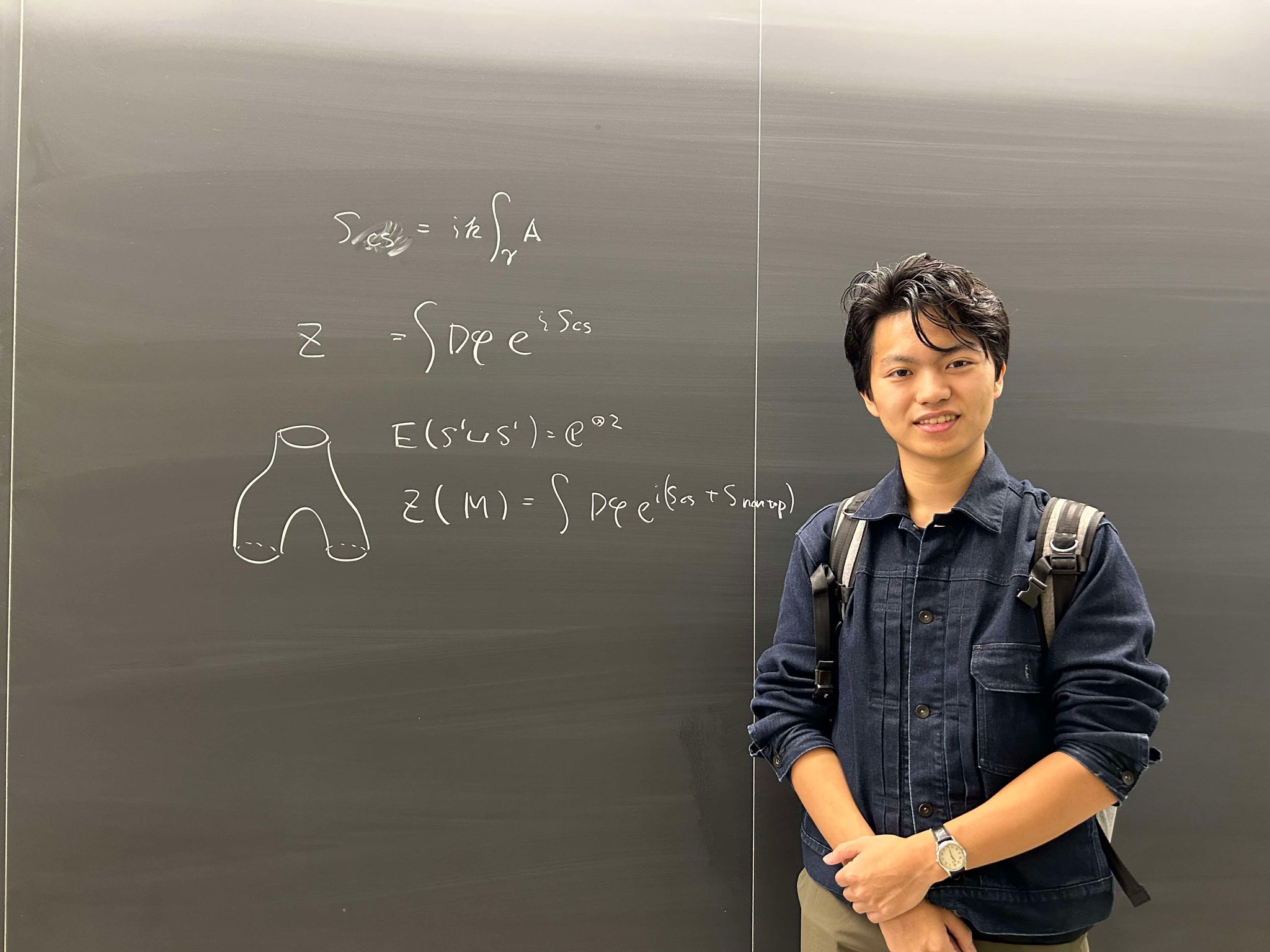
社会的な背景を踏まえた音楽の学びは、豊かな感性と人間力を育む大切な時間
【注目ポイント】
- 音楽での活動性や感性教育はバランスのよい精神状態を生む。
- 社会的、文化的背景を踏まえた鑑賞授業で社会的存在意義を認識。
- 新しい紳士像を体現する海外トップ大学進学者たち。
感性教育としての音楽を楽しむ
始業ベルの音とともに、生徒たちが合唱パートのテノールとバリトンに分かれて着席する。昨年夏にリニューアルした海城中学校の音楽室は「歌いたくなる空間」をコンセプトに校内コンペに勝ち抜いた生徒チームがプロデュース。教壇側の前方へ行くほど天井が高くなることで、声を出させる心理的効果があるという。
この日は音楽を選択した高3生の最後の授業ということで、ピアノ伴奏者として芸術科音楽の齋藤亮次教諭の大学の友人であり、同校オリジナルの合唱曲の作曲者でもある河谷萌奈美氏も参加。河谷氏の紹介時には「うおお〜!」と男子高校生らしい歓声が湧き上がる。まずは全員での身体のストレッチを行い、次に裏声で、低音で、少しずつ音量を上げて……など様々な発声練習で喉をリラックスさせた後に、いよいよ合唱のスタートだ。
まずは校歌を斉唱後、河谷氏のピアノ伴奏付きで歌い始めた。驚いたのは男子校にありがちなおふざけや、歌わない生徒はほとんど見られないこと。皆、譜面を目で追いながら、齋藤教諭の「ここから大きくなるよ〜!」といった歌唱中の指導に従い、4曲ほど滔々と歌い上げていった。
海城の合唱の授業は、昔ながらの授業の流れともいえる。しかし、受験とは関係しない感性教育として位置づけられる音楽の授業を生徒たちは、想像以上に楽しみ、没頭している様子が見てとれた。進学校である海城では高2、3年生ともなると受験勉強が本格化し忙しくなるが、音楽での活動性や感性教育はバランスのとれた精神状態を生み出すといい、「音楽だけでなく美術や体育の授業も人気があります」と齋藤教諭は教えてくれた。

マイナスイメージから出発する音楽教育
音楽は中学受験科目にないだけでなく、小学校の音楽教員との関係がうまく取れなかった経験から、音楽嫌いの新入生も多いという。このため、齋藤教諭は「中学3年間でマイナスイメージからゼロまで引き上げるのが目標。歌唱試験で重要な評価ポイントは大きな声で歌えること」と語る。
海城では中1~3年生と、高2~3年生の選択者に対して音楽の授業を実施している。中学では歌唱、アルトリコーダー、鑑賞(座学)をバランスに配慮しながら授業を行う。高校では斉唱、合唱が中心となり、これまでにミュージカルの名曲『Seasons of Love』や『Another Day of Sun』、また、あいみょん作曲、石若雅弥編曲『愛の花』なども扱ってきた。実は教科書に掲載されている合唱曲は共学校向きのものが多い。そのため、男子生徒の心に響くような詩や内容が盛り込まれた海城オリジナルの教材も作成し使用するようになった。今はその価値がわからなくても、大人になっていい曲だったと思えるような詩、そしてその内容にしっかりと関連づけて構成されている曲を選んでいるという。保護者から『子どもが音楽を好きになった』という声が寄せられるのは嬉しいと齋藤教諭は語る。
音楽の社会的側面を学ぶ「鑑賞」授業
海城の音楽の授業で特筆すべきは「鑑賞」だろう。クラシック音楽と西洋の歴史を関連させながら音楽史を学んでいく。ここには、単純な好き嫌いとは異なる視点から、音楽を捉えることの大切さ、面白さを生徒に知ってほしいとの意図がある。
実は、音楽は社会的、文化的背景と切り離せないものだ。例えば、ロマン派の音楽はロマンティックな曲が多いが、それはロマン派の音楽家が生きた時代がロマンとはかけ離れていたために、せめて音楽だけでもロマンある世界に浸りたいと思うような社会背景があった。「それまでの妖精の存在が信じられていたような時代から科学が発達し産業革命が起こり、神秘的なものが否定された時代です」と齋藤教諭。ロマン派の音楽は人間のそういった精神世界の喪失を補うような役割を果たしていたのだ。
また、音楽家が誰に向けて作曲したものかも社会的、文化的背景を知る上で欠かせない要素だという。例えば、バロック音楽の時代は、フランスのルイ14世の絶対王政全盛期にあたり、栄華を極めた貴族たちの生活を彩るBGMとしての音楽が数多く作られた。リュリやヘンデルは、貴族たちに雇われて彼らのために作曲したという背景があるわけだ。その後、音楽に大きな変化が起きる。ベートーヴェンの『交響曲第九番』は、非常にわかりやすいメロディーだが、それはフランス革命が大きく影響しているのだという。フランス革命による『人間は平等である』という思想は、世の中に深く浸透し、貴族のものであった音楽に全ての人々が参加するようになった。このため老若男女、誰が聞いても覚えやすいメロディーで作曲された。
齋藤教諭は「音楽家がどんな社会的、文化的背景のもとに生き、その作品を生み出したのかに思いを寄せながら、音楽の社会的存在意義も踏まえて鑑賞する楽しさを知ってほしい」と語る。その思いを汲むように、鑑賞の授業ノートを捨ててしまったことを後悔している、という卒業生のエピソードを教えてくれた。
また、齋藤教諭は社会全体に実利を生み出さない、数値化など目に見える評価がしづらい音楽を含めた芸術教育が苦しい立場にあるということに危機感を持つ。例えば、中1生がリコーダーでドレミが吹けたところで直接役に立つことはない。だが、小さな一歩であっても「新しい自分に変化していくことを大事にしてほしい」という。自分の変化への期待感を失わず、持ち続けることの大切さは、生徒たちの成長への期待感とも言い換えられる。それは失敗を恐れず挑戦し、自分と向き合い、自分を諦めない強い意志を育むことで、たくましく生きるための人間力を培う重要なものだ。齋藤教諭は、中1の授業の最初において必ず『自分が変わっていくことを大切にしよう』と話し、その思いを伝え続けている。

創立者の思いと海外大学への雄飛
海城の創立者である古賀喜三郎は若かりし頃、英国軍艦を訪れ、貴族出身の英国海軍士官の人間力に深く感銘を受けた。そして、リベラルかつフェアな精神を備えた『新しい紳士』の育成を志し、学校を設立したのが海城の始まりだ。グローバル化が進む国際社会や、多様な価値観が共存する日本の成熟社会で、『国家・社会に有為な人材を育成する』という建学の精神を時代に即して体現し、有為な人材に求められる『新しい学力』と『新しい人間力』を調和よく育む教育を実践する。
その教育の成果のひとつとして海外大学へと雄飛する海城生の輩出が挙げられる。これは模擬国連の世界大会で日本人初の最優秀賞にあたる事務総長賞を受賞した生徒のハーバード大学進学が端緒となった。海外大学も現実的な進学先となった生徒たちは、その後もカリフォルニア工科大学、トロント大学、マサチューセッツ工科大学など海外大学へ進学し続けている。そして彼らは一様に他者のために頑張りたいという思いも強い。カリフォルニア工科大学に進んだ卒業生は、在学中にも経済的に恵まれない子どもたちに自主的に数学を教える活動を行い、大学進学後も一時帰国時に「海外大学を目指す後輩たちのためのワークショップを開きたい」と母校に提案。これを受けて生徒と保護者を集めてのワークショップが開催されたという。
このように海城の『新しい紳士の育成』という教育目標は卒業生の姿にしっかりと反映されているようだ。
学校データ(SCHOOL DATA)
| 所在地 | 〒169-0072 東京都新宿区大久保3-6-1 |
| TEL | 03-3209-5880 |
| 学校公式サイト | https://www.kaijo.ed.jp/ |
| 海外進学支援 | 有 |
| 帰国生入試 | 有 |
| アクセス | 新大久保駅(JR山手線)徒歩5分 西早稲田駅(東京メトロ副都心線)徒歩8分 |
| 国内外大学合格実績(過去3年間) | ハーバード、マサチューセッツ工科、カリフォルニア工科、ミシガン、ジョージア工科、カリフォルニア、トロント、東京、京都、東京科学、一橋、東京外国語、早稲田、慶應義塾、上智、東京理科、東京慈恵会医科、順天堂など |
【関連情報】