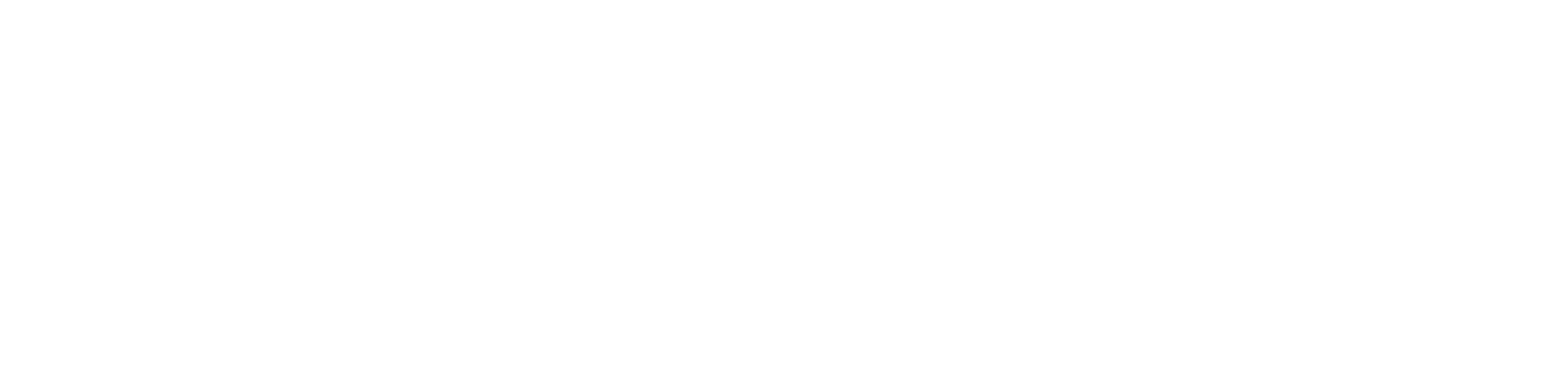生き方の軸をつくるキリスト教教育

注目のキリスト教教育
キリスト教教育が培う思考・行動のバックボーン
2015年の学習指導要領の改正により道徳が「特別の教科 道徳」として再編され10年。人格形成の黎明期にあたる中学生時代、確かな価値観の土台を築くための人間教育の重要性は、以前にも増して一層顕著になっている。そのような中、ミッション系私立中高の多くが、創立以来長年にわたり、キリスト教教育を基盤とした人間教育に取り組んでいる。本稿では「キリスト教教育が培う思考・行動のバックボーン」をテーマに独自の教育を実践し成果をあげる3校を取り上げた。各校はそれぞれ「聖書による多様な人間社会の疑似体験をベースに、深い思索と行動ができる人物を育成する」「確かな軸を持ち、行動心理まで踏み込んだ深い洞察力や共感力を育む」「まず他者の声に耳を傾け、『自らの生き方をもって語れる』人物を育成する」などの目標・指針を掲げ、キリスト教人間教育に力を入れている。

聖書による多様な人間理解をベースに深い思索と行動ができる人物を育成する
女子学院中学校 礼拝・聖書
Worship・Bible
女子学院で学ぶ意義を鵜﨑創院長は、「与えられた賜物を自分のためだけでなく、他者や弱い者に寄り添いながら世のため社会のために活かしていく。そのために自らに問い続け、知見を得るために学ぶ6年間」だと語る。この言葉を象徴するのが、毎朝の「礼拝」や週1時間の「聖書」の授業だ。
「礼拝」では、担当の教員や生徒が聖書を読み上げ、それをもとに奨励を行う。話のテーマは、聖書の解釈にとどまらず自分が失敗した、もしくは誰かを赦せなかったなど、生徒自身の体験と重なるものも多い。「人間は常に不完全な存在で、大いなる神の前では教員も生徒も分け隔てなく平等だということを、生徒たちは礼拝を通じて理解する」と、聖書科の石原教諭は語る。
また、「聖書」の授業では中1から新約聖書を読み進め、中3には旧約聖書を学ぶ。人類最初の殺人を記した『カインとアベル』をはじめ、罪深い人間の姿を捉えた物語も多い聖書から、生徒は何を感じ取るのか。「聖書を通じて自分が知らなかった多様な人間理解に触れ、それが個々の視野を広げる契機となる」と石丸教諭は語る。
このようにして、自分にはない価値観を他者が持っていることを知り、その価値観を受け入れ、自己を見つめ直す体験を日々積み重ねていく生徒たち。一人ひとりが大切な存在であるという「個の尊重」と同時に、個々が違った存在であることを認める「他者への理解」を深めていく。
彼女らの成長がはっきりと形になるのが、高3である。期末テストで、女子学院のキリスト教教育の根幹を成すテーマを掲げた論述課題に向き合う。前期のテーマは「愛について」。生徒たちは、聖書や古代から近代までの思想家の語る愛の理解に触れ、「愛について」自分の言葉で定義していく。後期は「自由について」。女子学院のなかで経験した自由について、近代の思想家たちと対話しながら、自分の言葉で、自分が経験した自由を論述していく。
6年間にわたり、生徒たちの「愛」と「自由」への思索は続く。こうした経験を礎に、深い思慮と、社会の風潮に流されることのない強い意志、行動力が醸成される。
(文/佐藤理子)

確かな軸を持ち、行動心理まで踏み込んだ深い洞察力や共感力を育む
恵泉女学園中学校 聖書・感話
Bible・Testimony
恵泉女学園は、キリスト教を土台とする人間教育と共に、『武士道』の著者として知られる新渡戸稲造の愛弟子であり、敬虔なキリスト教徒だった創立者・河井道の思想・生き方を教育の礎としている。
キリスト教教育では、一人ひとりが神に平等に愛されていることを知り、自らの存在の意味を発見し、他者と協力して生きていくことを学ぶ。『私たちは一人ひとり違っていていい、かけがえのない命である』という話に、ハッと驚く表情を見せる生徒も少なくない。
聖書科は「平和を作り出す女性の育成」のために河井によって設けられた、恵泉教育の土台である。中1では、様々な登場人物の人生を疑似体験することによって、行動の裏に隠れた人間心理への想像する。生徒は異なる考えをもつ他者を理解し、受容する大切さを学んでいく。毎日の礼拝における「感話」では、日頃感じたことや考えたことを文章にまとめることで、生徒は自己を見つめ、内面を掘り下げる経験を積む。また、聞く者を信頼し、時には真剣な告白となる感話を聞くことは、新しい価値観との出会いや先生・仲間の経験の追体験となり、他者を尊重する姿勢や共感力が自然と培われていく。
近現代の世界と日本について学ぶ高1の歴史総合は、平和を追求した河井の人生と思想を学ぶ教育とリンクしている。同校での授業は、河井の学園創立の思いと様々な苦労をたどることから始まる点が特徴だ。「第一次世界大戦後の世界について」というオリエンテーションでは、「河井先生が恵泉を設立しようと思ったのはなぜだろうか」という問いを投げかける。河井が学園を創設したのは奇しくも世界恐慌が起きた1929年であった。その後、日本は昭和恐慌に陥り、軍国主義化が進み、世界は戦争へと向かった。河井の当時の社会・時代との向き合い方、生き方について学び、平和を追求する女性を育成する学校設立の意義を考えていく。
また、1枚の写真や資料を題材に想像力を駆使して、人間心理にアプローチする授業展開も特徴だ。例えば、ヒトラーユーゲントの少年少女たちがヒトラーに熱い視線を送る写真を取り上げる。その背景には、ヒトラーの登場により苦境に立たされていたドイツ経済が好転し、苦しい生活から抜け出せたという事実がある。そこからヒトラーを英雄視した当時のドイツ国民の思いや心理を洞察させるのが狙いだ。
このように、同校のキリスト教教育は、社会の課題に取り組む際に、異なる状況下での人間心理や立場の違いにも目を向けながら思考する姿勢を育み、確かな自己の軸を育成することに大きく寄与しているのだ。
(文/松岡理恵)

まず他者の声に耳を傾け、「自らの生き方をもって語れる」人物を育成する
普連土学園中学校 沈黙の礼拝・宗教
Silent worship・Religion
『武士道』の著者で国際連盟事務次長も務めた新渡戸稲造と近代日本を代表する思想家内村鑑三がアメリカに留学中、キリスト教フレンド派の人々に進言し、女子教育を目的として創立された普連土学園。フレンド派の創始者であるジョージ・フォックスの言葉“Let Your Lives Speak.(自らの生き方をもって語りなさい)”をモットーに、「自由・平等・平和・対話」を教育の基軸として重視している。
毎週水曜日は言葉を発することなく過ごす「沈黙の礼拝」で静かに自己と向き合う。キリスト教で重んじられる三位一体論の〈聖霊〉を、フレンド派では〈内なる光〉と言い換えている。同校の青木直人校長は「〈内なる光〉は一人ひとりの中に内在しており、教会という権威を通さずとも、神様は各人に直接語りかけている。それを聴くために〈沈黙〉を大切にしており、フレンド派の信仰の本質でもあります」と語る。このことは、自己主張よりも他者の声にまず耳を傾ける姿勢を育む同校の教育の特色として表れている。普段の礼拝では生徒や教員が自由なテーマで考えていること、感じていることを話す場面が多い。「他者の話を聞いて多様な考え方に触れ、そこから気づきを得る。自分の世界が広がっていく。これこそが学びの原点だと考えています」と青木校長は言う。
2023年には、フレンド派の教え=「自らの生き方そのもので語れ」をまさに象徴するような異文化交流研修がスタートした。長年、カンボジアで地雷撤去活動を行うアキラー氏(カンボジア政府認可NGO団体・CSHD)を支援する献金を行ってきた縁で、現地に直接献金を届ける「カンボジア アキラー プロジェクト」と名付けられた研修が実現したのだ。現地では、生徒たち自ら防護服を着て地雷原に赴き、安全を確保した上で地雷や不発弾を間近に見て起爆装置のスイッチを押して爆破処理を行うなど、今もなお住民がさらされている危険と隣り合わせの現状を体感した。また内戦による土壌汚染で通常の農耕が困難な土地が多くあるが、この状況を打破するために設立された水耕栽培の実験農場を見学する機会も設けられた。これがきっかけで土壌汚染問題に興味を抱いた生徒は、帰国後、東京農業大学の土壌学研究室を訪問した。彼女は将来、環境保全に携わる仕事に就くことを目指し、勉学に励んでいるという。
キリスト教フレンド派は歴史的平和教会の一つであり、様々な平和運動や奉仕活動に従事してきた。1947年にはそれらの活動の功績が認められ、アメリカ・フレンズ奉仕団とイギリス・フレンズ協議会はノーベル平和賞も受賞した。普連土学園の教育にはその崇高な精神が脈々と流れているのだ。
(文/菅原淳子)