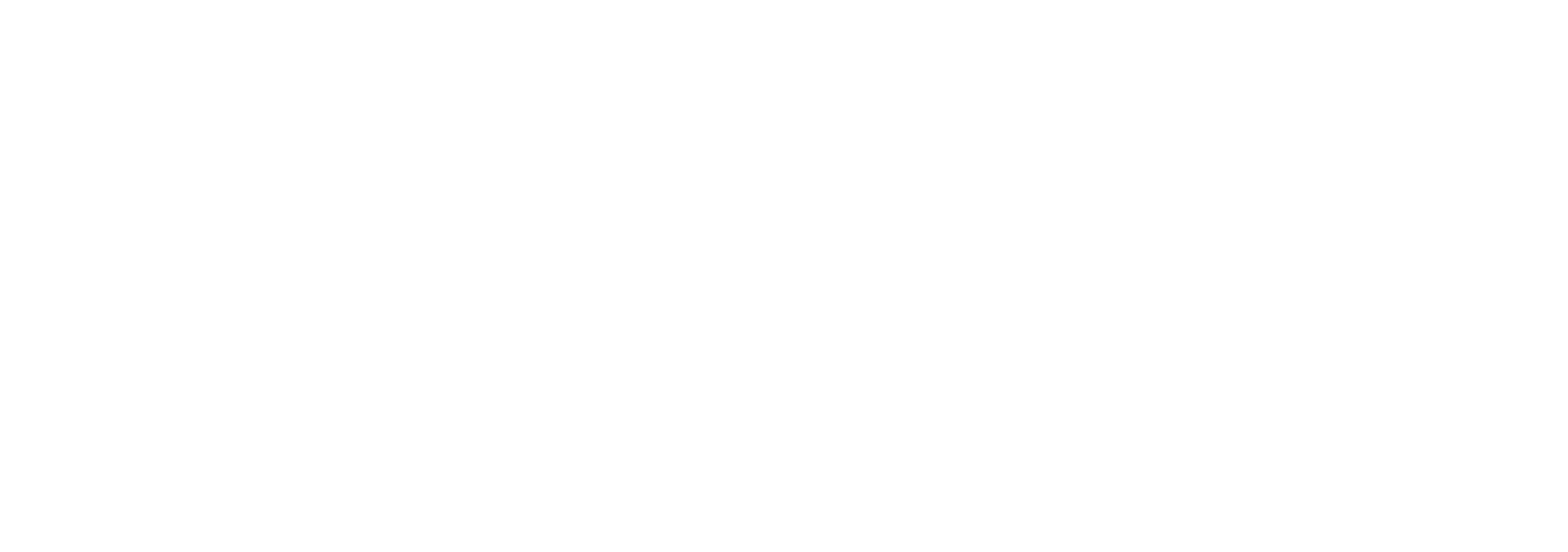新しい社会を切り開く美術教育をめざせ!

注目の美術教育
新しい取り組みが広がり始めている教育現場
従来の表現技術の枠を越え、生徒たちの創造性と社会課題への洞察力を育む重要な学びの場として注目を集める現代の美術教育。急速に変化する社会において、美術は単なる芸術表現の手段ではなく、批判的思考、共感力、課題発見・解決能力を育むクリティカルな学習分野へと進化を遂げている。これらの美術教育を通じて、生徒たちに自分たちの創造性が社会をより良い方向に導く可能性を実感させることも狙いの一つだ。本稿では「西洋美術を中心とした徹底した基礎教育を段階的に積み重ねる」「生徒の成長に合わせて課題の幅を広げ、美術の学びを社会へとつなげる」「優れたデザイン思考の実践活動のベースにはアート思考をきわめる教育がある」「中高と大学の美術教育が接続されることで社会を変える大きなの力が生み出される」といったユニークな美術教育を実践する4校を紹介していく。

各自の個性を伸ばし、人間として成長させることを第一に考える共立女子中学校。美術教育にも重点をおき、多彩なプログラムを展開している。中高合わせた6年間の流れとして段階的な学習を積み重ねることで、効果的に発達段階に応じた表現の成長を目指す。幅広いジャンルを設定しながらも通底するものは西洋美術を中心とした徹底した基礎教育だ。
まず中1ではデッサンにはじまり、形の測り方や、光と影の捉え方、構図の考え方などの基本を幾何形態から自然物へと応用させながら時間をかけて習得する。次の油彩画静物では初めて触れる油絵の道具も本格的なものを揃え、古典技法を学びながら油彩画のプロセスを理解できるよう教員も同時にレクチャーしながら授業が進められていく。デッサンにしても油彩にしても、まずは対象を丁寧に観察し向き合う姿勢をつくる時期として教員は重要視している。日頃、目にしているものを知ったつもりになりがちな情報社会において、描くことによって理解し、関心や愛着に変化する生徒の内なる気づきにつなげる狙いもある。
中2では中1で培った基礎力をもとに「自画像」を制作する。多感な時期に自分とじっくり向き合い、観察を通して写実を目指しながらも、自由な色彩の表現には自己の内面が表出した充実感のある作品が多く、中学3年間の山場となっている。その後の発展としてCDジャケットやアニメーションの制作などデジタルの課題が中3まで続き、これまで古典的な技法で育んできた技術や感性を現代の表現方法に応用して、生徒の表現の幅を広げるとともに3年間で美術史を体験的に外観できる流れとなっている。
高校ではさらに創造性が求められる段階となる。中学での「見えるものを描く」から「イメージ(想像力)」や「コンセプト(制作意図)」が制作の重要なプロセスとなり、それらを練るには自己の関心や社会性、世界観が問われる。高1での漫画表現や高2の抽象画表現、高3でのボックスアート(立体オブジェ)などの課題を通し、正解のない問いに自分がどう応えるか、様々な技法や素材、表現方法を超えて迷う時、積み重ねてきたオーソドックスな基礎力や美術史などの知識が支えとなって、作品の完成度に発揮されていると教員は実感する。
また、その生徒の成長を絶え間なく支えているものとして、多くの美術作品に囲まれている環境があげられるだろう。校内には至る所に絵画が飾られており、画家の肉筆を間近に見ることができる。生徒にとっては無意識の日常だが、その日々の積み重ねは心の豊かさに貢献し、卒業後も自分なりの美の基準を持って生きることができる人間に育つことを同校は期待している。
(文/坂井彰代)

桐朋女子中学校では、創立当初から芸術教育に力を注いでおり、6名もの専門教員が美術の授業を担当している。この充実した指導体制により、東京藝大を始めとする名門美術系大学への進学も視野に入れた専門的な学びが展開されている。
桐朋学園は音楽系名門大学を擁することからも分かるように、歴史的に芸術への造詣が深い。中学1年生では「音楽」=週2時間、「美術」=週2時間、「書道」=週1時間の必修授業があり、高い専門的知識を備えた教員による高度な授業が行われている。
特筆すべきは、中3から始まるユニークな主専攻・副専攻制だ。生徒は興味関心のある科目を主専攻として選び、副専攻として3科目を3期に分けて学ぶことができる。この手厚い芸術教育体制により、普通科に在籍しながらも芸術系大学への進学を視野に入れたレベルの高い授業が受けられる。これこそが桐朋女子の強みであり、予備校や画塾に頼らずとも、授業内での取り組みや教員の個別サポートだけで進学が可能となっている。
美術教育における最大の特徴は、学年を追うごとに課題となる対象物の幅が広がっていくカリキュラム構成だ。中学では、観葉植物の写生や野菜の模刻から始まり、自画像の制作、環境のためのポスター、ピクトグラム、リトグラフへと展開していく。これは、自然→人→環境→社会という流れで、対象への視野を段階的に広げていく工夫が見られる。美術を教える高田雄一郎教諭によると、最初は対象物の“観察”に重きを置き、そこから徐々に自身の“発想”を加えて表現していく課題編成にしているという。
高校ではさらに発展し、利用する相手を想定した創作絵本やレコードジャケット、知育玩具、公共性に根ざしたデザイン制作など、課題そのものが社会性を帯びていく。桐朋女子が力を入れているのは、作品制作の過程で目的(Why)やターゲット(Who)、ロケーション(Where)などの観点を設定しながらテーマを模索することだ。
高田教諭は「美術が向かい合う先は、社会です。生徒たちには作品制作を通して社会に意識を向けてほしい」と話す。この「美術を通して社会に貢献する人材を育てる」という教育理念は、現代の美術教育が目指すべき方向性を示しているといえよう。
(文/佐久間香苗)

実業家でありながら、教育・文化にも情熱を傾け山種美術館の創立者としても知られる山崎種二が創設した山崎学園。美術教育では単なる技術習得を超え、社会と深く結びついた創造的思考力を育成する。その特徴は、デザインとアートを二本柱に「多様な視点を統合し、ヒトモノコトに新たな関係性を見出し、新たな意味や価値を創造する」という明確な教育目標にある。
デザインでは、他者の要望と自分の発想をすり合わせてアイデア提案を行い、課題解決を目指すデザイン思考を育んでいく。創造的思考力の実践を通して社会と関わり合い、学びが社会とつながっていることを実感することを狙いとし、企業と連携した教育も積極的に行う。例えば、「キヤノンマーケティングジャパン(株)との連携プロジェクト」では、新商品のVlog撮影に特化したビデオカメラをZ世代に販売するためのマーケティング施策を考案し、その施策を後押しするVlog作品も提案。「一つのコミュニティーで一つのカメラをシェアして、撮るコミュニケーションを促す、コミュ×カメ」を提案した同校チームは1位を受賞、全4賞中の3賞を同校が受賞した。うち1チームは社会実証を行うに至った。
一方のアート(絵画)では、自分なりの視点で世界をみつめ、自分なりの答えを見つけていくアート思考を育む狙いがある。そのためには、自分が何に価値を見出すのかという根幹部分を明確に持つこと、この点が重要となっていく。このアート思考をさらに深め、より感性を育むべく導入された授業が日本画だ。日本画の素材、色材はどのようにできているのか、その背景にはどのような見方があるのかを学ぶ。授業は創設者・山崎と日本画のつながりにも及び、最終的には日本画を実際に描くほか、同校所蔵の日本画を用いるなど様々なアプローチで理解を深める。これらの学びは、日本独自の表現方法や発想、ひいては日本文化、日本の美意識の再認識にもつながっていく。また、「自分たちの背景にある日本画への理解は、日本文化のみならず、他国の文化も尊重する気持ちが育まれ、多様な視点を持つことの大切さを知る端緒となる」と美術科の杉原誠教諭。そして自国の文化への深い知見は、国内外の社会や科学の世界に新しい発想や視点を提示し、よりよい社会を考える創造的思考力の育成へとつながっていく。
このように同校の芸術教育はデザインとアートを独立させた学びとはしていない。そこには、デザイン思考育成のベースには、豊かな創造性と感性を育むと共に自分独自の価値観の核心を認識するアート思考が不可欠との確固たる思いがあった。
(文/松岡理恵)

ビジネス界でデザイン思考とアート思考が大きな注目を集める昨今、女子美術大学付属中学校の教育に熱い視線が注がれている。AIの台頭により「オリジナリティや人間にしかできないこと=美術」という認識が広がるなか、同校の美術教育はまさに時代が求める人材育成と見事に合致しているのだ。
同校が重視するのは、単なる技術習得ではなく、個性に裏打ちされた一人ひとりの「好き」を育てることだ。「デザイン思考やアート思考の根幹には『個』の存在があります」と広報部主任の並木憲明教諭は語る。型にはめず、個々の生徒の「らしさ」を尊重し、育てる教育環境の中で、生徒一人ひとりの創造性と独自性が花開いていく。
中高の美術教育は段階的な学びを特徴としている。中1・2では絵画やデザインの既存の枠組みを超え、ダイナミックな作品制作を通じて、描く喜びそのものを体験。中3では、構図や明暗の捉え方といったより専門的な絵画表現を学び、同時にデザインの授業で地域に根ざしたパッケージデザインや公園の遊具をテーマに、実社会に役立つ創造的な課題に取り組む。
デザインは単なる表現ではなく、依頼者の希望に対応しながら、デザイナー独自の自由な発想を付加する、より社会と密接に結びついた営みである。高1では「絵画」「デザイン」「工芸・立体」をそれぞれ学び、高2からは自らの「好き」を追求するため、これらのコースから1つを選択して集中的に学ぶ。
同校の教育は高校卒業後も続く。8割以上の生徒が女子美術大学に進学し、さらに専門性を深める。2023年に新設された「共創デザイン学科」は、現代社会のニーズに応える先進的な学科だ。
この学科の特徴は徹底的な実践型学習にある。学生たちは、企業が直面する複雑な社会課題や市場ニーズを深く分析し、革新的なソリューションを提案する。地域の課題解決や持続可能な製品開発、ユーザー体験の再設計など、実社会で求められるリアルな課題に、多角的な視点とデザイン思考で挑む。プロジェクトでは、企業の担当者や異分野の専門家と対話し、調査とプロトタイピングを繰り返す。そのプロセスを通じて、学生たちは課題発見力、対話力、構想力、チームワークなど、これからの時代に不可欠な実践的スキルを磨き上げていくのだ。
同校の最大の強みは、受験勉強に惑わされることなく、自分の内なる「好き」を深く追求できる環境にある。中学で自分の好きを見出し、高校でそれを極め、大学でさらに社会との接点を広げていく。こうした一貫教育は、何らかの型にはまることが求められることが多い現代社会において、生徒たちの個性を大事にし、相似形で大きく育てていくものだといえるだろう。
(文/佐久間香苗)