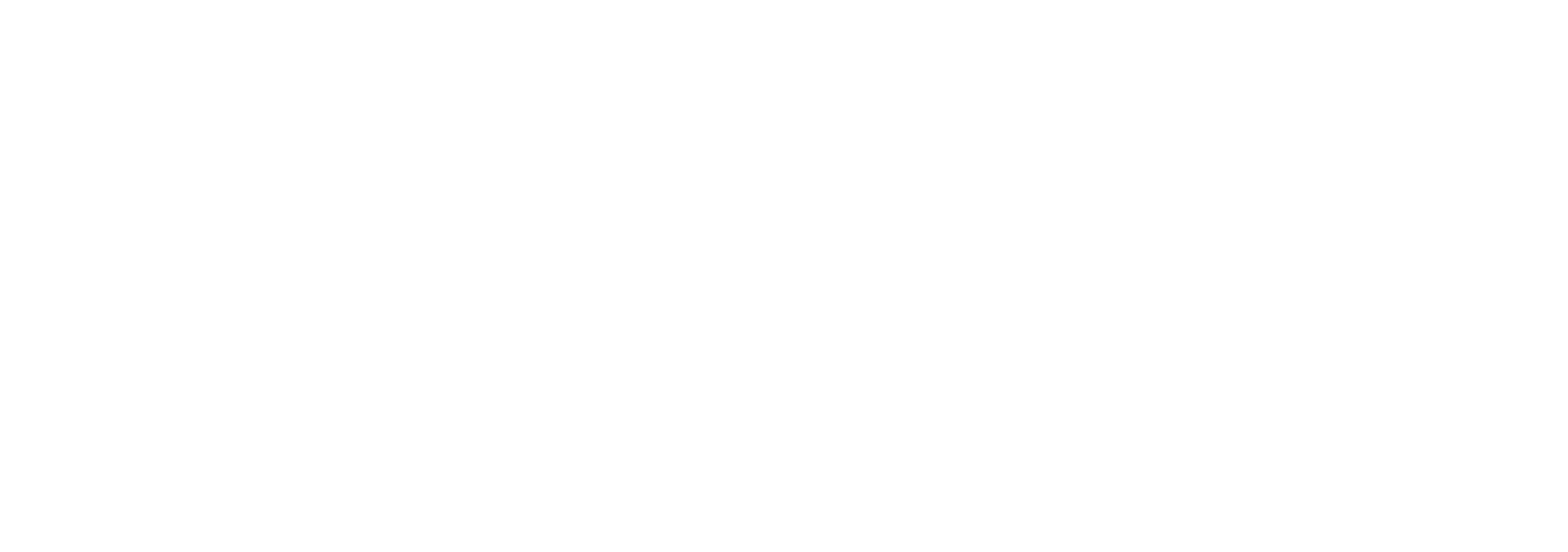自分の世界を切り開く読書の魅力を発信する図書館

図書館探訪(巣鴨学園)
本を味方に、自立を促す~本との出会いで成長する生徒たち
スマホや動画に囲まれる日常のなかで、近年、生徒の読書傾向は「よく読む層」と「ほとんど読まない層」とに二極化している。巣鴨学園においてもその傾向は見られるが、一方で、本と出会い、変化していく生徒たちの姿が確かに存在している。図書館を拠点に、「教職員」、図書に関する企画や日常的な業務を担う部活動の「図書総務」、各クラスから選出された「図書委員」たちは、3つの立場から読書の魅力を伝える活動に取り組んでいる。読書を通じて育まれた想像力、思索、知的好奇心──巣鴨学園で本と向き合う生徒たちの言葉から、「読書することの意味」をあらためて探っていく。
巣鴨学園の図書館は、生徒の学びを支え、心に寄り添う役割を担う。常連の生徒は日常的に図書館に足を運んでおり、読書好きな巣鴨生にとって学内における、教室以外のもう一つの居場所にもなっている。
通常は昼休みと放課後に、平日は午後5時半、土曜は午後3時まで開館。貸出は1人5冊まで、2週間借りることができる。2階建て構造で、静かに、ゆったりと過ごせる空間だ。1階の座席は高校生専用、2階の座席は中高校生共用となっている。現在、専任司書1名、英語教員でもある司書教諭1名、国語・社会・理科の担当教員5名の計7名で運営され、各教科の知見を活かした選書も行う。蔵書数は3万5千冊。新聞・英字新聞(計7紙)、雑誌(日本語・英語合わせて37誌)も置かれている。特に医学、数学、生物、歴史、物語、小説に関連する本は巣鴨生に人気で、蔵書も充実している。
読書の魅力をPRする取り組みとして新刊図書や特別企画などの展示コーナーを設ける。展示テーマは、修学旅行などの学校行事や、授業で紹介された本など。印象的なのが英語教員の司書教諭が担当する英文に和訳を添えて解説する展示だ。毎年テーマを変えて継続され、2023年度は「医療英語とは」と題し、医学部入試で出題された英文を紹介。昨年度は「日本文化を英語で紹介」として、10のトピックに分類し、日本の食や風習などを解説した。本年度は「日本人が英語で著した書籍」をテーマに、本の内容を紹介しながら、英語原文と日本語訳を併記した掲示を行っている。掲示の下には関連書籍を並べ、英語に親しむきっかけとして、また英語を入り口に本を手に取る動機づけとして、実用的かつ魅力的な構成となっている。
こうした活動には、ジュンク堂書店池袋本店とコラボレーションし、池袋駅を通学で利用する学校で取り組んだ企画「巣鴨・豊島岡・立教池袋の先生と生徒たちがおすすめする中高生のための書店」(2020~21年)に参加した経験が、少なからず反映されている。各校の生徒・教員が推薦する本を、自作のPOPと共に店頭に並べたこの企画は、新型コロナのために当初の計画ほどには実現できなかったが、生徒たちにとって本や実社会との接点を実感する機会となり、その後の図書館内での展示につながっている。
「本をたくさん読みたい、しっかり勉強したい――生徒たちのそんな希望を叶えつつ、彼等の自立を自然と促す場所。それが図書館であってほしい」。司書は図書館の役割をそう語った。「館内は静かだけれど、熱い気持ちで生徒が心地よく活動できる居場所作りをしたい」。そこには、本は生徒たちの味方であってくれるはずだとの強い思いが感じられた。
「図書総務」はいわゆる文化系クラブのような位置づけで、図書館を拠点に本に関する様々な取り組みを行っている。現在、部員は中1〜高2までの十数名。火曜日昼休みのミーティング、シフト制での貸出業務担当のほか、読書の魅力PRのために出来ることは何でも行おうとしている。
直近の活動としては、国会図書館や大手出版社への見学訪問や、豊島区立上池袋図書館で行われた企画展示「一箱本棚」への参加、ジュンク堂書店での「選書ツアー」だ。「一箱本棚」は「頭脳戦」や「戦後80年」など生徒独自のテーマで10〜15冊を選び、本棚に展示して来館者に紹介する企画である。また「選書ツアー」は図書館に入れる本を生徒が書店で選定する企画で、毎回ひとつのテーマを決めてそれに合う本を選んでいる。これらの企画は不定期で刊行される『図書館だより』で部員のおすすめ本などと共に紹介され、巣鴨生に新たな読書体験を促している。
そのほか、文化祭では「図書館脱出ゲーム」を企画。館内の本を使った謎解き形式で、参加者が設問やヒントを元に問題の答えを本から探し出す体験を通じて、図書館の魅力を自然に体感できる仕組みとなっている。例えば、問題文には「浅草を舞台とした川端康成の小説のタイトルに含まれる色は何か」といった内容が盛り込まれ、参加者は検索機を使うなどして本を探し、最終的にキーワードを完成させて図書館からの脱出に挑む。
このように図書総務の活動は多岐にわたるが、その活動を通じて読書への向き合い方が変化した部員もいる。高2のEさんは、かつてほとんど本を読まなかった。「読む暇がない」が口ぐせだったが、一冊の小説をきっかけに物語世界に没頭するようになった。今では医療ミステリーに惹かれ、特に巣鴨卒業生の医師であり小説家でもある知念実希人の作品に影響を受け、さらには医学分野の書籍へとその興味は広がっている。テレビドラマをきっかけに医師志望となったEさんにとって本は、その思いをさらに強くする出会いでもあり、人間の不安や希望に寄り添う言葉の宝庫でもある。一方、高2のNさんは、尊敬する先輩の姿に憧れて図書総務に入った。もともと読書はアニメの原作小説程度だったが、推薦図書の中から気になった一冊を手に取り、そこから読書の習慣が生まれた。現在は社会の仕組みを知るような本へとその関心が広がっている。また、活動を通じて「読まないけれど読んでみたいと思っている人」に本の魅力を伝えることに意義を見出している。
現在『図書だより』の月刊化、中学生向けの棚の拡張などを新たな目標に掲げる中学生の部員たちは、ただ図書館を支える集団ではない。そこには、次の読者へ本を手渡す役割を担おうとする想いがあり、本と巣鴨生をつなぐ確かな架け橋となっている
「図書委員」は、各クラスから2名ずつ、立候補または教員からの依頼で選ばれる。当番制で図書館に来て、返却作業や書架整理、推薦図書のPOP制作、本の紹介活動などを通して図書館を支えている。一人一人の活動頻度こそ多くはないが、皆が使いやすい図書館を目指して、委員たちは日々図書館の維持管理にいそしんでいる。
もちろん、なかには相当な読書家もいる。
幼少期の長期入院をきっかけに読書の世界に没頭するようになったTさん(高3)は「娯楽は本しかなかった」と振り返る。彼にとって、物語は孤独を包み込む存在だった。論説文よりも小説を好むのは、著者の主張ではなく、著者との対話を楽しめるからだという。「本を読み続けることで、必ず心に響く言葉やストーリに出会える」と語るTさんは、『竹取物語』(角川書店ビギナーズクラシックス版)、芥川龍之介の『鼻』、そして冒険の魅力あふれるアレクサンドル・デュマ『三銃士』をお薦め本にあげてくれた。
「その時に目についた本を、迷わず読む」──そんな読書スタイルを貫いてきたのがKさん(高3)だ。特定のジャンルに縛られず、小説、エッセイ、SF、評論まで広く読み進めてきた。「読書は想像力を鍛える営み」と語り、その場に書かれていない“背景”を読み取る力が大切だという。「ちょっと時間があれば図書館に立ち寄って欲しい」と語るKさん。彼が薦める辻仁成『ミラクル』や幸田文『木』、浅田次郎『壬生義士伝』は、そうした想像力を掻き立ててくれる一冊だ。
言語習得のために絵本を使って育てられた幼少期の経験から、本との距離が常に近かったSさん(高3)は「読書とは世界の解像度を上げること」と語る。本を読むことで得た先人の思考や知識によって、自分の生きる現実がより鮮やかになり、楽しめるという。例えば、公園を歩くとき、ただの風景が知識によって意味を持ちはじめる──その感覚を読書が与えてくれたという。「読書で何かを得ようとすると疲れるので、楽しむことを最優先にして欲しい」と語る彼は、深く考えることの楽しさや作家の世界観が堪能できる、御子柴善之『自分で考える勇気』、今井むつみ『言語の本質』、京極夏彦『姑獲鳥の夏』をお薦めしてくれた。
3人からの“未来の巣鴨生”へ向けたメッセージに共通するのは、本は単なる情報ではなく、自分の世界を切り開く道具であるという点だ。本を介して世界と対話し続ける彼らには、しなやかな知性と好奇心が溢れていた。
(文/松岡理恵)