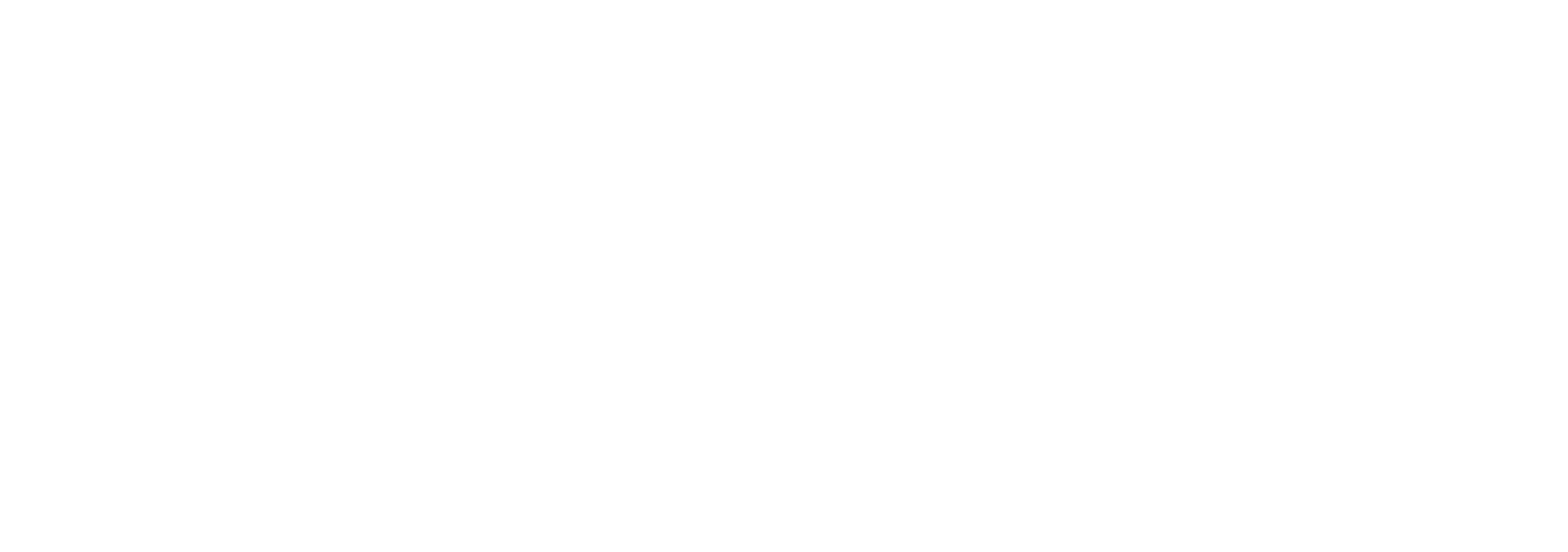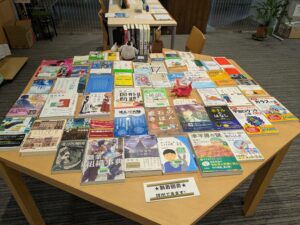自由な視点と思考力を育む対話型絵画鑑賞法
鈴木 通代
すずき みちよ
愛あることばに会い、I (私)のことばを育む “あい・ことば” 代表
<Profile>
静岡放送(株)報道制作局アナウンス部に⼊社。ニュースキャスター、ラジオパーソナリティーなど TV・ラジオの報道番組、ワイド番組、⾳楽番組など幅広く担当し、同時にディレクター、プロデューサーを務める。同社報道制作局情報センター副部⻑、ラジオ局編成制作部⻑、㈱静岡新聞社 SBS学苑本部局次⻑を務めた。キャリアコンサルタントの資格を取得後、コミュニケーション、ビジネスマナー、メンタルトレーニング、 京都芸術⼤学で対話型鑑賞などを学び、30年のアナウンサー経験を活かして、現在「スピーチコンサル」「朗読」「対話型鑑賞」などの講座や講演をはじめ、企業研修の講師として「アート思考&コミュニケーション」を広げる活動をしている。また、絵本未来創造機構のEQ絵本講師として、絵本の持つ可能性を⼦育て中の保護者など⼤⼈に伝えている。

アナウンサー業の役に立つのではとすすめられて体験した対話型鑑賞の魅力とポテンシャルに心を惹かれ、退職後にフリーアナウンサーとして活躍する傍ら、対話型鑑賞のアドバンスコーチ資格を取得。現在はファシリテーターとして積極的に関わっている鈴木通代さんに対話型鑑賞の教育的側面について興味深いお話しを伺った。
(文/高島正人)
子供たちの『考える力』『生きる力』を育む対話型鑑賞法
美術作品の作者や時代背景といった予備知識は一切不要、むしろ先入観を排して自由な眼で作品に触れることで、誰もが美術作品について臆することなく話し合うことができる。語るのには専門知識が必要と思われがちな分野で、知のブレークスルーを起こしているのが「対話型鑑賞法」だ。
対話型鑑賞は、1980年代後半から90年代にかけて、ニューヨーク近代美術館(MoMA)で、当時の教育部部長フィリップ・ヤノウィン氏らによって確立された。絵画など一つのアート作品をグループで鑑賞し、個々が作品の中に何を見たか、どんな感情を持ったかを話し合う。
美術館ではしばしば学芸員によるギャラリートークが行われているが、実際のところ参加者はその内容をほとんど覚えていないという。「一幅の絵を見る時間、どのくらいだと思います?」と茶目っ気たっぷりに尋ねる鈴木さんによると、その平均はわずか十数秒。作品よりも、そこに添えられたキャプションを読む時間のほうが長いくらいだ。この事態に危機感を覚えたのがMoMAの関係者。芸術作品が人々にどのように役立つかを検証し、まずはアートをより深く理解するための方法として、ビジュアル・シンキング・カリキュラム(VTC)を開発。さらに発展させたビジュアル・シンキング・ストラテジーズ(VTS)を日本語で表現した言葉が「対話型鑑賞」だ。これまでの鑑賞法とは全く違う視点に立ち、学芸員ら専門家からの話を一方的に聞くのではなく、見て聞いたあとに自分で思考するプロセスを重視するのに加えて、参加者同士の「対話」を組み込んでいるのがこのプログラムの特徴となる。
対話型鑑賞の基本プロセスは「見る」「考える」「話す」「聞く」の4つ。これを数名のグループで繰り返しながら20分程度行う。まず「見る」では、作品を隅々まで観察する。よく観察することで、ふとした疑問や、惹かれる興味が自分の中ではっきりしてくる。次に「考える」では、観察で気づいた事柄をもとに、作品の中で何が起きているか、それはどういうことなのかといった問いを立て、自分なりに思考を深める。
深めた考えを他者に伝えるのが「話す」で、できるだけ相手に伝わるように自分の思ったことを言葉にする。最後に、今度はグループの人たちがそれぞれどこを見てどう思ったかを「聞く」のだが、ここでは否定をせずすべてを受け入れる気持ちで聞くことで、自分にはなかった視点からの気づきを得る。
「サイクルの繰り返しは平面的な周回ではなく、螺旋を描いて高まっていくので、参加者それぞれの思考が深まり進化していくことになるのです」と鈴木さん。つまりサイクルを重ねるたびに初見で見た作品世界が広がりを持ち、まったく異なる世界を体験できるようになる。これが対話型鑑賞の特徴だ。
対話型鑑賞を続けることで、次の7つの能力が育まれる、と鈴木さんは語る。
1)作品から情報を引き出す観察力
2)何が起きているかを考える想像力
3)観察と想像を組み合わせて得た考えや感情の動きを客観的にまとめる論理的思考力
4)それを言葉にする言語化能力
5)同様にして発信される他人の話をよく聞く傾聴力
6)話し手の考えや感情を受け入れる他者理解力
7)自分と異なっていてもそれを否定しない受容力
そして、5~7を通じて得られる多角的な視点と、それらを材料にさらに観察し想像を働かせることで得られる主体的に考える力は、単に作品鑑賞をするための能力という枠を飛び越えていくと鈴木さん。「ですから、時間をかけてじっくり育んでいってあげれば、生徒たちの『自分で考える力』が高まって、未来で何が起きても対応できる『生きる力』につながっていくじゃないかな、って思うんです」
「正解がない」のが対話型鑑賞の正解
一幅の絵を題材に選んだとして、その絵の知識は一切不要。むしろ邪魔になるからと、題名や作者、制作の背景といった情報がまったくないところから観察を始める。「一般的な教育では正解を求めがちですよね。でも、正解のないところから自分で考える、正解はない前提でものごとを考える、というのを重視しています」事前に情報があると、それを正解だと思い込んでしまって、作品を眺めるときの枷になり、発想が広がらなくなるためだと鈴木さんは強調する。
「生徒はすんなり入りやすいのですが、ある程度の美術的素養を持つ大人の場合、題材に知っている絵が出てきたときに自分の知識をどう覆して発想を広げられるかという戦いになりますね」そのため、頭が柔軟な子どものうちから対話型鑑賞の基本サイクルに慣れておくことは、成長したのちにも効いてくるのだ。
鈴木さんは、具体的にどのようにして参加者の発想を広げるファシリテーションを行っているのだろうか。基本的な問いは「この絵(作品)を見て、何が起きていると思いますか?」「それはどこを見てそう思いますか?」というシンプルなものだという。ここで「なぜそう思う?」という問いかけをしないのには訳がある。「なぜ」に対する答えは、往々にして個々人の心の中で完結していることが多く、言語化しづらいうえに、参加者との共有が難しい。だが、「どこ」と尋ねれば、容易に絵の具体的な箇所を指し示すことができる。「みんなと共有できる答え方を導く問いが重要なんです。指し示された箇所をみんなで見ることで、それぞれの考えがまた生まれてくる。「そこから、ほかに気がついたことはありますか? 発見したことは?と質問を重ねて、視点を変えながら観察の対象範囲を広げていくことができるのです」
具体的に答えられる問いなら、生徒たちにとっても発言しやすい。正解を求められていないので、自分の思ったことも言いやすい。学校の授業の中で試みたことのある先生方からは、「普段発言しない子も、これなら発言できると思うのか、積極的に話してくれるようになった」という実績もあるという。
だから鈴木さんは、ファシリテーターとしての自らの役割を、教える立場ではなく参加者と一緒に考える立場と位置づけ、全員が気持ちよく話せる環境を作り、それぞれの発言を拾い上げて全員が発想を広げ、新たな視点や表現を学ぶ機会を提供することに注力している。「参加者の発言は否定しないで受け止めます。たとえ自分の考えていることとはまったく違っていたり、誤りではないかと思えたりしても、例えば『ポストが赤い』と言うけれど、それがポストではないと思っても訂正はせず、本人に見えていることを尊重しながら、鑑賞体験を紡いでいきます」
対話型鑑賞の教育現場における実践と効果
まっさらな気持ちで作品に触れ、自分なりに見て感じたことを素直に語る参加者。ファシリテーターはそれを否定することなく、どこを見てそう感じたか、作品のどこからその考えを得たかの整理をする手伝いをする。生徒たちが気後れせずに参加できるこの鑑賞法の実践事例を教えていただいた。
まず先進的な取り組みとして、愛媛県立美術館の学芸員である鈴木由紀氏が自著にもまとめている「愛媛対話型授業プロジェクト」が挙げられる。2013年に「朝鑑賞」と銘打って導入し、これを2015年から文化庁の補助事業として4年間実施するなかで、生徒たちの学習意欲が向上するなどの成果が実証されたという。
対話型鑑賞のプロセスである「見る・考える・話す・聞く」はあらゆることに通底する基本的な能力であるため、美術以外にも多様な教科に応用が可能だ。国語では読解の幅を広げ、理科では人体の構造を自ら発見し理解する一助となり、体育では苦手な運動を克服するヒントを得られ、家庭科では料理を栄養面で改善する方向性を探り、さらに部活動ではチームワークを向上させ地区大会優勝を導いた事例もあるといい、基本的な力であるがゆえに応用の可能性を感じさせる。
見方も自由、発想も自由、語る内容も自由という対話型鑑賞だけに、ファシリテーターには、偏見のない中立性や、深い洞察、予測される参加者からの発言への適切な対処能力など幅広い力が求められる。「よいファシリテーターはよい鑑賞者であれ、と言われます。まずは自分が鑑賞者として確立している必要があるのです」自らの鑑賞能力を駆使し、参加者の発言をどのように共有し、発展させ、異なる意見や見方をどうつなげていくかが腕の見せどころだ。そのためには専門の育成機関で学び、一定の技術を身につける必要がある。
「生徒たちの基本能力を底上げするのに対話型鑑賞はきっと役立ちます。ぜひ教育現場に取り入れて試してほしいと願っていますし、常に生徒たちと一緒に過ごしておいでの先生なら、どういう声かけをしたらこの子が反応してくれるかみたいなところまで手が届き、問いかけもしやすかったりするのではないかという点からも、学校の先生がファシリテーターをやっていただけるのであればそれが一番いいなと思います。ただ、現実にはなかなか難しいかとも思いますので、そこはわたしたち専門のファシリテーターや、地域の美術館の学芸員の方々にご相談いただいて、よりよい実践機会を作っていければ。朝礼や終礼の時間を月1回充てるとか、可能な範囲で試みてみるのはいかがでしょう」
こう語る鈴木さんは学校現場での対話型鑑賞普及に前向きで、「ボランティアを含めてさまざまな協力が可能です」と明るい笑顔を見せた。
同じ作品を題材にしても、参加者や実施状況が異なればまるで違う話が展開され、同じ話は二度と聞けないのが対話型鑑賞のおもしろさ。4人程度集まればオンラインでも実施可能な手軽さも兼ね備えている。一度でも体験すると理解がぐっと深まり強く興味を惹かれるのは、試しにやってみた鈴木さんが今や自らファシリテーターとして最前線で活動していることでも明らかだ。
ご自身がメディアで活躍する鈴木さんだけに、対話型鑑賞を通じて醸成される「自分で考える力」は、「報道を鵜呑みにしないメディアリテラシーの育成にもつながりますね」と持論を話してくださった。現代の若者たちが好むYouTubeやTikTokなどの映像情報も、見たものをそのまま真実だと思い込まず、作り手の意図や編集の可能性を考え、「本当にこれは正しいのか」「ほかの人からはどう見えているのか」など、多角的かつ柔軟に考える視点を養えるという。鈴木さんは、これからを生きる若者たちに欠かせない視点を育てる点でも、多様な側面から対話型鑑賞法の可能性を見出しているのだ。
混沌とした未来を生きる次代の子どもたちには、自らの道を照らす光を身につけてもらいたい。その一助になり得るプログラムとして、活用を検討してみてはいかがだろう。
お問い合わせ
| 名称 | あい・ことば |
| 公式サイト | https://ai-kotoba.net/ |
| info@ai-kotoba.net |